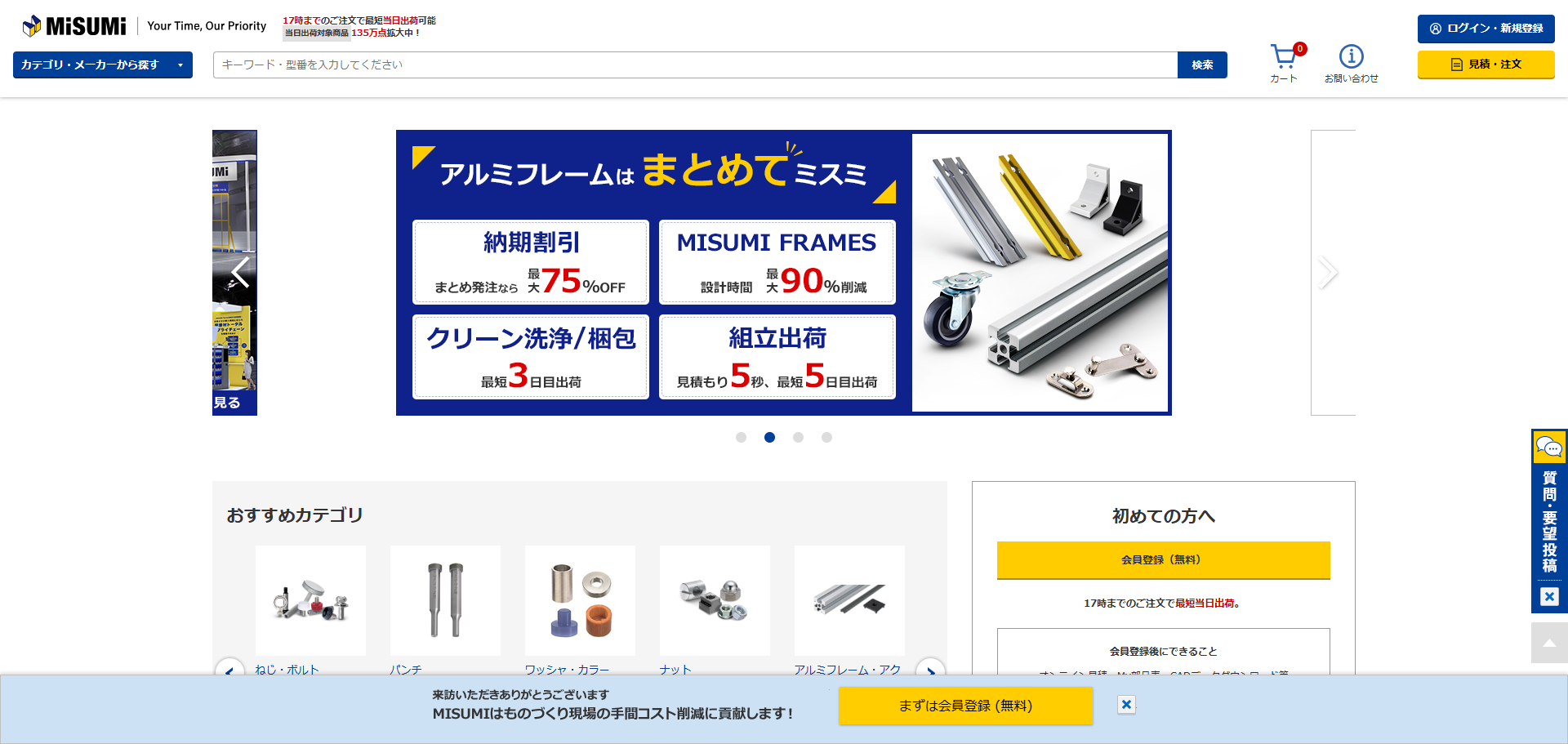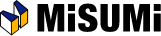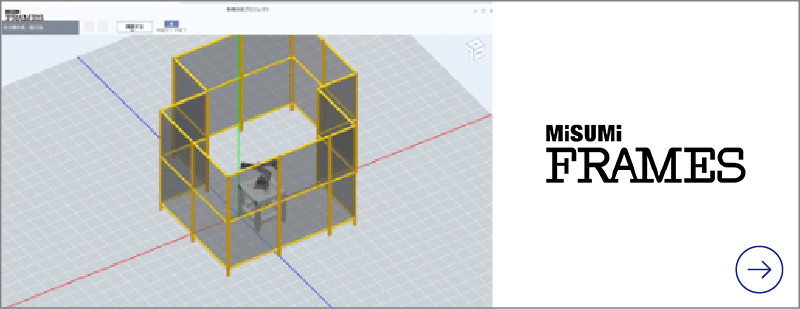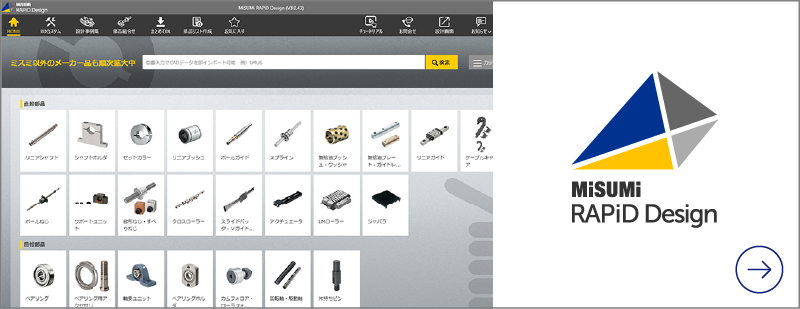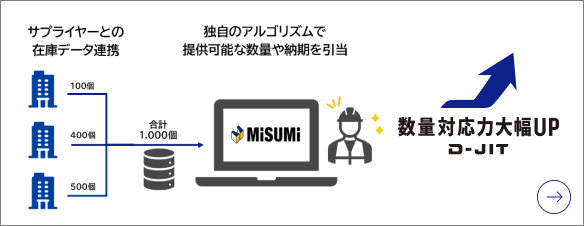ミスミモデルの進化を図り、顧客の時間価値向上に貢献するために、当社グループでは
-
高い成長志向
-
戦略性
-
能動性
を全社員が発揮すべき「実践力」として設定しています。この「実践力」を発揮し、挑戦し、結果を出し、また次の挑戦に向かう。 やった人(挑戦して成果を出した人)には高く報いる。 これらを有機的、持続的に作動させるためには、整合する人事制度が必要です。 当社グループでは、23年度より以下を「ミスミグループ共通の人事戦略」として定め導入を進めています。
評価制度
評価制度
ミスミ・バリューズの発揮度合(実践力)とその結果を問う評価の2モジュールから構成しています。
- 実践力評価:
-
成長性、戦略性、能動性、組織活用度について、
実際に発揮された「行動」(ミスミ・バリューズ実践力)を評価する仕組み
- 成果評価:
-
ストレッチな目標に対する達成度を評価する仕組み
実践力評価に使用される項目は、「正しい視点」(「Think/See right」)の指針に従い、ミスミ・バリューズに基づく思考と実践を表す具体項目として職位・職種を問わず「ミスミで働く社員」に求める最重要要素として、グローバルに共通の設定としています。
成果評価では、各組織の「ビジネスプラン」(後述)に設定されたストレッチの度合いと同じストレッチ性を各個人の目標に予め織り込むことで、全組織で戦略と整合した目標に向けた挑戦を引き出すとともに、社員の挑戦や成果を正しく認識し、正しく報いる仕掛けとしています。
報酬制度
報酬制度
「正しい視点」(「Think/See right」)の指針では、社員の挑戦や成果を正しく厚く報いることを目指しており、「やった人(挑戦し、成果を出した人)」に市場上位の総報酬水準で報いること、を当社グループでは報酬の基本コンセプトとしています。
そのコンセプトに適した報酬を各地域の習慣・法的枠組みに即した形で設定しています。
たとえば、ミスミ日本地域においては、社員の報酬構成や運用を下記のように設定しています。
- 基本給:
-
職責に応じた基本報酬
- P賞与:
-
組織の「成長度合い」に応じた賞与
- B賞与:
-
全社の「利益創出」に応じた賞与
- 株式報酬:
-
幹部社員に対する中長期貢献への報酬
これらのミスミ人事戦略の取組みは、まずは日本で先行導入しています。今後、各国の事情に合わせた形に調整を加えながら、順次、グローバルへの展開を予定しています。